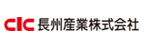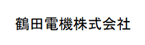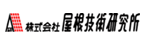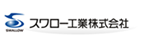【2027年ZEH基準改正】住宅の省エネ性能が大幅強化へ|新基準の全容を徹底解説
2025.09.15

目次
2027年度からZEHの基準が大きく変わろうとしていることはご存じでしょうか?
日本の家づくりが変わるため、抑えておくべき内容になっています。
✅本記事の内容
- なぜ今、ZEH基準の改正が必要なのか
- 2027年度から何が変わる?新ZEH基準の4つの柱
- 2027年度 新ZEHの4つのグレード|あなたの住まいはどのレベルを目指す?
- 2027年施行のZEHによって得られる4つのメリット
- 2027年施行のZEH制度が抱える2つのデメリット
- 押さえておきたい今後のスケジュール
- 2027年に備えてZEH基準の見直しの概要を理解しよう
✅本記事の信頼性
・現役の某太陽電池メーカーの営業マン「スポンジ」が監修(営業キャリア10年以上)
・営業実績は、住宅用太陽光発電を200棟/月を販売継続(3年以上)
・住宅用蓄電池を30台/月を販売継続
本記事では、新しいZEH基準では具体的にどのような内容が変更になるのかが理解できるようになります。
他工務店やビルダーとの差別化ポイントをどのように作っていくかも、今後家を売っていくためには重要な要素です。
どのような家づくりをしていくのか、新ZEHに向けて考え直すための良い機会になります。
なぜ今、ZEH基準の改正が必要なのか

政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、住宅分野は重要な役割を担っています。
家庭部門からのCO₂排出は国内全体の約15%を占め、省エネ化の遅れが目標達成の大きな障害となっています。
そこで2027年度から導入される新ZEH基準は、断熱・省エネ・創エネを抜本的に強化し、すでに動き出している「GX志向型住宅」と同等レベルの性能を求める内容となりました。
工務店や設計責任者にとって、これは単なる規制強化ではなく、顧客に対し“環境配慮型の高性能住宅”を提案できる絶好の機会です。
地域工務店が大手と差別化を図るには、こうした基準改正を先取りし、補助金や最新技術を活用した提案力を強化することが鍵となります。
2027年度から何が変わる?新ZEH基準の4つの柱
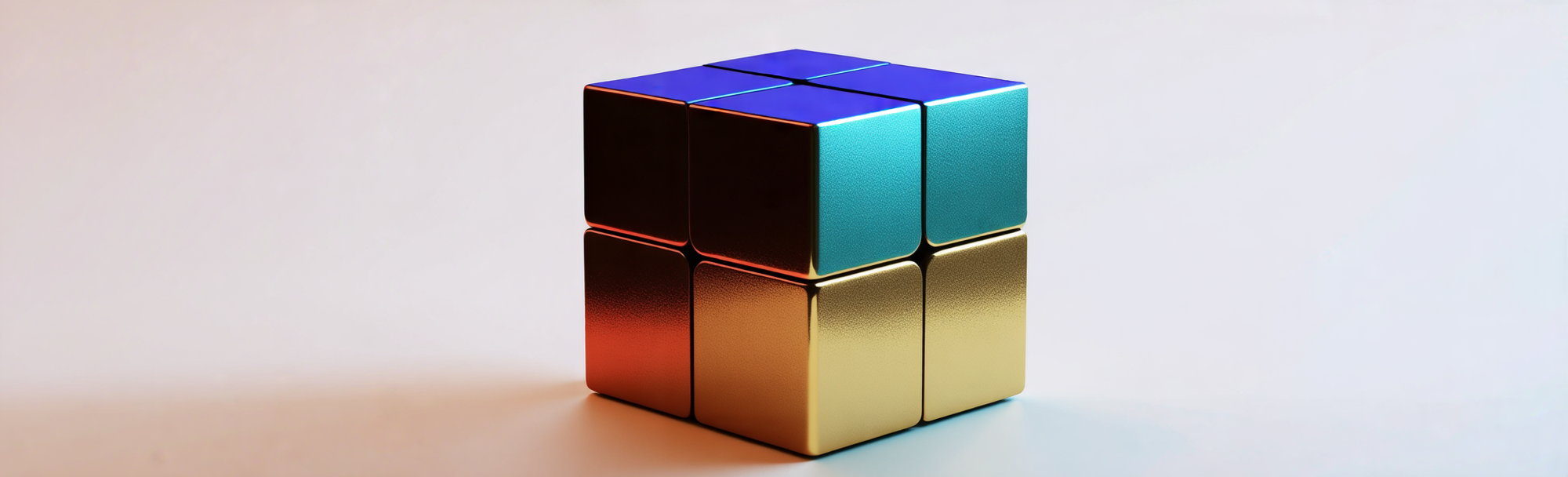
2027年度から施行される新ZEH基準は、住宅の省エネ性能を大幅に底上げするための4つの柱で構成されています。
・断熱性能を等級5から6へ引き上げ、UA値の基準を厳格化
・省エネ性能は現行の20~25%削減から一律35%削減へ強化
・設備要件としてHEMSと蓄電池(5kWh以上)またはV2Hの導入が必須化
・創エネ性能ではZEH+の削減率が115%以上へ引き上げ
工務店や設計責任者に求められるのは、これらの要件を総合的に満たす設計力と提案力であり、大手との差別化を図る絶好のチャンスでもあります。
断熱性能の大幅強化:等級5から等級6へ引き上げ
新ZEH基準の大きな変更点の一つが断熱性能の引き上げです。
これまで等級5で十分とされていた基準が、2027年からは等級6が必須となり、UA値(外皮平均熱貫流率)の基準がより厳格に定められます。
壁には高性能な断熱材をより厚く施工し、窓にはペアガラスからトリプルガラスへと切り替えることが求められます。
これにより冬の暖房効率や夏の冷房効率が大幅に改善され、光熱費削減にも直結します。
一方で、従来の工法の延長では対応が難しく、資材調達や施工方法の見直しが必須です。
工務店にとっては新しい技術習得と提案力強化の機会であり、早期対応することで地域市場における差別化につながります。
省エネ性能の引き上げ:エネルギー消費量35%削減
現行ZEHでは再エネを除き20%以上(ZEH)、25%以上(ZEH+)の削減が求められていました。
しかし新基準では一律35%削減へと強化されます。
15ポイントもの引き上げは単に高効率機器を導入するだけでは到達できず、建物の断熱性や気密性を高めたうえで、照明・給湯・空調など住宅全体のエネルギー消費を最適化する必要があります。
さらに住まい手の生活スタイルに応じたエネルギーマネジメントも欠かせません。
つまり、設計段階からの総合的な省エネ提案が重要であり、工務店にとっては単なる設備販売ではなく「住まい全体の省エネ設計」を提供できるかが競争力を分けるポイントとなります。
設備要件の追加:スマート化と自家消費の促進
新基準で注目されるのが、設備要件としてHEMSと蓄電池(5kWh以上)またはV2Hの設置が必須となる点です。
これにより、太陽光で発電した電力を効率的に家庭内で消費できる仕組みが整い、停電時にも最低限の電力供給が可能となります。
つまりZEHは単なる省エネ住宅ではなく、災害に強いレジリエンス住宅としての価値を持つようになります。
工務店や設計責任者は、エネルギーの自家消費を前提にしたシステム提案が求められる時代に突入したといえます。
特に地域密着型の工務店にとって、防災性や安心感を付加価値としてアピールできることは、顧客から選ばれる大きな要素となるでしょう。
創エネ性能の強化:ZEH+は115%以上の削減へ
新基準のZEH+では、一次エネルギー消費量削減率が従来の100%以上から115%以上へと引き上げられます。
これは住宅が消費する以上のエネルギーを生み出し、余剰分を地域に供給することを意味します。
つまり、住宅が「小さな発電所」として機能し、脱炭素社会に直接貢献する存在へと進化するのです。
工務店にとっては、太陽光発電の設置容量や蓄電池との組み合わせを戦略的に設計する力が問われます。
顧客にとっては光熱費ゼロどころかプラスの価値を生む住宅となり、地域に誇れる暮らしを実現できるのが魅力です。
こうした未来志向の提案ができるかどうかが、2027年以降の競争力を大きく左右します。
2027年度 新ZEHの4つのグレード|あなたの住まいはどのレベルを目指す?

2027年度からの新ZEH制度では、住宅の性能に応じて4つのグレードが定義されます。
最上位の「新ZEH+」は115%以上の一次エネルギー削減を実現し、余剰電力を地域に供給する住宅です。
次の「新ZEH」は100~115%未満の削減を達成し、家庭のエネルギー収支をゼロ以下に抑える標準モデル。
「Nearly新ZEH」は75~100%未満で、完全なゼロには届かないものの大幅な省エネを実現します。
そして「新ZEH Oriented」は多雪地域や狭小地、6階建以上の集合住宅など特殊条件の住宅を対象に、太陽光発電は必須ではなく推奨とされています。
工務店はこれらの違いを理解し、顧客の地域特性やライフスタイルに応じた最適な提案を行うことが差別化につながります。
[新ZEHグレード一覧]
・新ZEH+:115%以上削減、地域に電力を還元
・新ZEH:100%以上115%未満、標準的な省エネ住宅
・Nearly新ZEH:75%以上100%未満、大幅な省エネを実現
・新ZEH Oriented:多雪地域・都市部狭小地・6階建以上集合住宅、太陽光は推奨
新ZEH+
新ZEH+は新基準における最高水準のグレードで、一次エネルギー消費量の削減率が115%以上と定められています。
つまり家庭で使用するエネルギーを上回る量を創り出す「マイナスエネルギー住宅」です。
太陽光発電と蓄電池を組み合わせ、余剰電力を地域へ供給することで、家庭の自立性を高めると同時に社会全体の脱炭素化にも貢献します。
工務店にとっては、地域の未来を支える先進的な住宅を提案できる格好のチャンスであり、施主にとっては光熱費ゼロを超えて収益を生む可能性を秘めています。
まさに次世代の住宅モデルとして、差別化の切り札となるグレードです。
新ZEH
新ZEHは一次エネルギー消費量を100%以上115%未満削減する、いわば標準的なゼロエネルギーハウスです。
家庭の年間エネルギー収支をゼロ以下に抑えることが可能で、電気代の大幅削減を実現しつつ快適な生活を送れます。
工務店にとっては最も提案しやすいモデルであり、幅広い顧客層に適応可能です。
高断熱・高効率設備をバランス良く取り入れつつ、補助金制度を組み合わせることで費用負担も抑えられる点が強みです。
特に「光熱費の心配をなくしたい」「将来のエネルギーコスト上昇に備えたい」と考える顧客に向け、安心して勧められる現実的な選択肢といえるでしょう。
Nearly新ZEH
Nearly新ZEHは一次エネルギー消費量を75%以上100%未満削減する住宅を指します。
完全なゼロには届かないものの、従来住宅と比べて大幅な省エネを実現できる点が特徴です。
予算や敷地条件などの制約からZEH基準を満たすのが難しい場合でも、このレベルであれば現実的に導入可能なケースが多く、施主にとっては「できる範囲で省エネを最大化する」柔軟な選択肢となります。
工務店にとっては、顧客の条件や要望に応じて提案の幅を広げられる点が強みです。
また、補助金や自治体の支援を活用すればコスト負担を軽減できるため、省エネ意識が高まりつつある顧客層にアピールしやすいグレードといえます。
新ZEH Oriented
新ZEH Orientedは、多雪地域や都市部の狭小地など、物理的制約から太陽光発電の設置が難しい住宅を対象とした緩和型のモデルです。
具体的には積雪荷重の大きい地域の戸建てや、敷地に余裕のない都市部の住宅、そして6階建以上の集合住宅も含まれます。
太陽光発電は必須ではなく「推奨」にとどまりますが、断熱や省エネ性能の基準はしっかり求められるため、一定の性能担保は必要です。
工務店にとっては、厳しい立地条件や規模の大きい集合住宅案件でも提案できる柔軟な選択肢となり、顧客への幅広いアプローチが可能になります。
地域事情や敷地条件に合わせて最適なプランを示せる点で、他社との差別化にもつながります。
2027年施行のZEHによって得られる4つのメリット

2027年から施行される新ZEH基準は、住宅性能を飛躍的に高めるだけでなく、住まい手や工務店にとっても大きなメリットをもたらします。
まず光熱費削減による経済的効果は、電気代高騰が続く今こそ施主に強く響きます。
次に断熱・気密性向上による快適性と健康性の確保。
さらに、蓄電池やHEMS導入により災害時でも電力を確保できる安心感が加わります。
そして資産価値の維持・向上という長期的メリットも見逃せません。
これら4つの要素は、顧客にとって「経済・健康・安心・資産」のすべてに直結する魅力であり、工務店にとっては競合他社と差別化できる絶好の提案材料です。
以下ではそれぞれのメリットを詳しく解説していきます。
光熱費の削減
新ZEHの導入による最大のメリットは光熱費削減です。
例えば、5kWの太陽光発電と5kWhの蓄電池を組み合わせた場合、年間で約15万円、15年間で合計180万円の電気代削減効果が期待できます。
電気料金が高騰する中で、この数字は施主にとって非常に説得力があり、初期投資の回収シナリオも具体的に描けます。
さらに再エネの自家消費が増えることで、電力会社からの購入量を抑えられる点も魅力です。
工務店や設計責任者にとっては、単なる“省エネ住宅”ではなく“家計を守る投資商品”として提案できるため、競合との差別化にも直結します。
数字で裏付けられた提案力が、顧客の安心感を高めるのです。
快適性と健康性の向上
新ZEH基準で求められる断熱・気密性能の向上は、光熱費だけでなく居住者の快適性や健康にも直結します。
冬場でも家全体が暖かく、夏は外気の影響を受けにくいため涼しい空間を実現できます。
特に部屋間の温度差が小さくなることで、入浴時などに発生しやすいヒートショックのリスクを大幅に軽減できるのは大きな魅力です。
また結露やカビの発生が抑えられ、アレルギー疾患の予防にもつながります。
顧客にとっては「健康を守る住宅」としての価値が高まり、工務店にとっては生活の質を支える提案として差別化が可能です。
性能数値だけでなく、暮らしの質の向上を訴えることが受注拡大の鍵になります。
災害時の安心感
新ZEH基準で必須化される蓄電池とHEMSの組み合わせは、災害時のライフライン確保に直結します。
停電が発生しても、蓄電池にためた電力で照明・冷蔵庫・スマホ充電など最低限の生活を維持できるのは大きな安心材料です。
さらにV2Hを導入すれば、電気自動車を住宅に給電することも可能で、数日間の電力供給をカバーすることができます。
地震や台風など災害リスクの高い日本において、住宅が“電力のシェルター”として機能することは、施主にとって強い魅力となります。
工務店は災害対策という視点で提案することで、単なる省エネ住宅以上の付加価値を示せます。
レジリエンスを備えた住宅こそ、次世代に選ばれる家づくりです。
将来の資産価値を守る
新ZEH基準を満たす住宅は、将来の資産価値維持においても大きな優位性を持ちます。
省エネ性能が高い住宅は中古市場でも高く評価され、リセール時の価格下落リスクを抑える効果が期待できます。
一方で基準を満たさない住宅は今後ますます評価が下がり、売却や相続の際に不利になる可能性があります。
特に2030年にすべての新築住宅がZEH水準に引き上げられれば、その差はさらに鮮明になるでしょう。
施主にとっては「快適で経済的」なだけでなく「資産を守る家」としての価値が加わります。
工務店がこの視点を踏まえて提案できれば、将来を見据えた賢い選択肢として顧客から高い信頼を得られるはずです。
2027年施行のZEH制度が抱える2つのデメリット

新ZEH基準には多くのメリットがありますが、一方で工務店や施主が理解しておくべき課題も存在します。
最も大きいのは「初期費用の上昇」と「高度な技術力の必要性」です。
断熱材やトリプルガラス、蓄電池やHEMSなどの設備導入により建築コストは増加し、従来より10~15%の上昇が見込まれます。
また、設計・施工の難易度が上がり、省エネシミュレーションや設備の最適組み合わせを判断できる知識も不可欠です。
こうしたハードルは確かに負担となりますが、補助金や人材育成を活用することで克服可能です。
工務店にとっては、課題を逆に「信頼性を高める提案材料」として活かすことが差別化につながるでしょう。
初期費用の上昇
新ZEH基準では、断熱材の強化、トリプルガラス窓、HEMSや5kWh以上の蓄電池といった設備が標準化されるため、建築コストは従来より10~15%上がる可能性があります。
これは施主にとって大きな負担に見えますが、国の補助制度を活用すれば軽減可能です。
例えば「GX志向型住宅補助金」は最大160万円/戸が支給され、さらに住宅ローン控除の優遇や自治体独自の補助金も併用できます。
工務店にとっては、こうした支援策を顧客にわかりやすく案内できるかどうかが信頼獲得のポイントです。
単に「コストが増える」ではなく「補助金で賢く負担を減らす方法」を提案することで、競合との差別化を実現できます。
技術力・専門知識の必要性
新ZEHは、省エネ・創エネ・蓄電・スマート制御を総合的に組み合わせた高水準住宅です。
そのため従来の施工経験だけでは対応が難しく、設計段階からのシミュレーションや設備選定の最適化など高度な知識が求められます。
特に断熱設計や電力マネジメントに精通していなければ、基準を満たすプランを成立させることは困難です。
ここで重要となるのが、ZEHビルダー登録事業者としての実績や研修体制の整備です。
工務店にとっては、社員教育や外部セミナーの活用を通じて技術力を底上げすることが急務です。
施主に「最新基準を安心して任せられる会社」と認識されれば、地域におけるリーディングカンパニーとして存在感を高められるでしょう。
押さえておきたい今後のスケジュール

新ZEH基準への移行は段階的に進められており、工務店や設計責任者はそのスケジュールを正確に把握しておくことが不可欠です。
まず2025年4月にはすでに全新築住宅で「断熱等性能等級4以上」が義務化され、省エネ性能を満たさない住宅は建てられなくなりました。
そして2027年度からは新ZEH基準の認証が始まり、同時に現行基準での新規認証は停止されます。
ただし、2027年度までに建設された住宅の改修については現行基準での認証が可能です。
さらに2030年度には、省エネ基準そのものがZEH水準へと引き上げられる予定です。
つまり、あと数年で新築住宅のすべてがZEH性能を持つ時代が到来します。
早めに準備を整えることが競争優位につながるのです。
2027年に備えてZEH基準の見直しの概要を理解しよう

2027年から施行される新ZEH基準は、住宅業界にとって「義務」であると同時に「チャンス」でもあります。
確かに建築コストの上昇や技術力の強化といったハードルは存在しますが、国の補助金制度や最新設備の活用により十分に克服可能です。
むしろ、この基準改正を先取りして取り組むことが、競合との差別化を生み出す大きな武器となります。
工務店や設計責任者に求められるのは、顧客に「光熱費削減」「快適な住環境」「災害時の安心」「資産価値の維持」といった多面的なメリットを提示し、将来を見据えた家づくりを提案することです。
2027年を待つのではなく、今から準備を進めることで、地域に選ばれる存在へと成長できるでしょう。